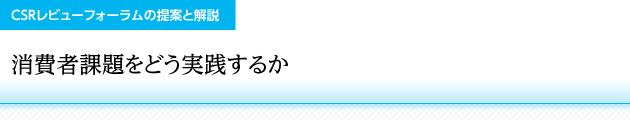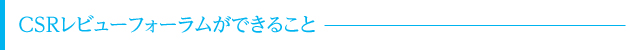�劲�F�ÒJ �R�I�q
�u����҉ۑ�v�����H���邽�߂̃|�C���g�ɂ��āA����2�̊ϓ_������܂��B
Ⅰ�D�u�����\�ȏ���v�ւ̒���
Ⅱ�D�u����҉ۑ�v��CS(�ڋq����)�Ƃ͈Ⴄ�̂��H
�Ō�ɁACSR���r���[�t�H�[�������ł��邱�Ƃ����`�����܂��B
- Q.�u����҉ۑ�v��1�ł���u�����\�ȏ���v�ɒ��ڂ��W�܂��Ă���̂͂Ȃ����H
- A.�����������̂悤�ȏ��i��T�[�r�X�̑I���E����𑱂��Ă�����A�����\�Ȓn����Љ���������邱�Ƃ͂ł��܂���B
�����\�ȎЉ�������ɂ́A����҂����݂̃��C�t�X�^�C�������������Ƃ��s���ł��B
��Ƃ́A�����\�Ȑ��i�Â�����M�A����ɂ͏���ҋ���Ȃǂɂ���āA����҂ƂƂ��Ɂu�����\�ȏ���v�ւƐi��ł������Ƃ����߂��Ă��܂��B
- Q.�ǂ�Ȏ�g�݂���������̂��H�]���̊��ɗD�������i�Â���̉����ł������̂��H
- A.�����\�Ȕ��W�ɂȂ��邩�ǂ����A���|�C���g�ŁA����҂Ƃ̊W���̌����������߂���B�P�Ɏ��Ђ̏��i�E�T�[�r�X�����z�����Ă��邩�ǂ����ł͂Ȃ��B
ISO26000�ł͑g�D�ւ̊��҂Ƃ��āA���̂悤�Ȏ�g�ݗ�������Ă���B
�i1�j���ʓI�ȋ���i�\�͂�^����A����p�^�[���̕ω����̕��@�ւ̏����Ȃǁj
�i2�j�Љ�I�A���I�ɗL�v�Ȑ��i�E�T�[�r�X�̒i�}�C�i�X�̉e���̏����E�ŏ����A�ė��p���\�Ȑv�A�����\�Ȕ��W�ɍv���ł��鋟���Ǝ҂̗D��A����҂ւ̐��i�E������̒A�Љ�I�E���I�ɗL�v�ȏ��̒Ȃǁj
- Q.�����߂����̓I�Ȏ�g�݂͂��邩�H
- A.��ɂ́A���J���B���Ƃ��A����҂̃��C�t�X�^�C���̌������ɂ͏���҂̍s���𑣂���Ƃ̏��J�����s���B���Ђ̗ǂ����g�݂����������̂ł͑���Ȃ��B��ɂ́A����ҋ���B�����\�ȎЉ��S���l�ނ̈琬�͏���҂݂̂Ȃ炸��ƂɂƂ��Ă��d�v�B����ҁi�c�́j�Ƌ������Ď�g�ނ��Ƃ����߂����B
![]()
- Q.CS(�ڋq����)�Ƃǂ��Ⴄ�H
- A.�]���A�g�D�i��Ɓj�́A���q���܂ɑ��ACS�̍l�����Ŏ�g��ł��܂����A�u����҉ۑ�v�̎�g�݂Ƃ́A�ȉ��̓_�ō��{�I�ɍ��ق�����܂��B
�� CS�͎��g�D�̔��W�̂��߁AISO26000�́u�Љ�̎����\�Ȕ��W�ɍv���v�������
�u���j���v�́u�Љ�I�ۑ�v�̈�Ƃ��āA���̖ړI�͎����\�Ȕ��W�ɍv�����邱�Ƃɂ���܂��B
�� �Ώێ҂̈ʒu�t�����قȂ�
��q������A���݂́u���q���܁v�����ł͂Ȃ��A���ڋq�Ƃ��Ă̏���ҁA�����̏���҂��l���ɓ��ꂽ���g�݂��K�v�ł��B
![]()
- Q.CS�̎��g�ݕ���́u�i���v��u���q���ܑΉ��v�����S�����A����Ŗ��͂Ȃ����H
- A.ISO26000�ł�7�̏���҉ۑ肪�ݒ肳��Ă��܂��B�������Q�l�Ɍ��݂̎�g�ݓ��e���������Ă݂܂��傤�B�d�v�Ȃ̂́A�g�D�i��Ɓj������̎Љ�I�ӔC�͈̔͂�F�����āA����҂̒u���ꂽ����̉����Ƃ��Ď��g�D���v���ł���ۑ�ɂ��āA�D�揇�ʂ����߂Đi�߂邱�Ƃł��B
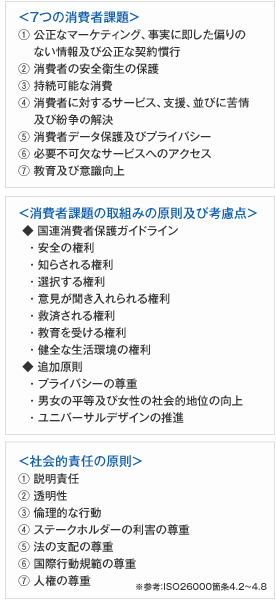
![]()
- Q.�]���A����ɂ��Ă�CS�̔��z�ōs���Ă��邱�Ƃ��������AISO26000�ƈقȂ�̂��H
- A.����҂̌�����Љ�I�ӔC�����Ȃǂɂ����g�݂��K�v�ł��B
�� ���g�݂̍l�����̊�{�͢����҂̌����
�]��CS�̎�g�݂Ƃ��ẮA�j�[�Y�ւ̑Ή��A�s���̉�������̉����ɉ����A����҂ɂƂ��Ẳۑ�̉���������҂̌����̎��_�Ŏ��g�ނ��Ƃ����߂��܂��B
�������A�����Ȃ�u����҂̌����v�Ɋ�Â���g�݂͂ނ��������̂ŁA�ŏ��͎��Ђ̎�g�݂̃`�F�b�N�Ƃ��Ďg�p���Ă͂ǂ��ł��傤���B
�� �Љ�I�ӔC�̌����Ɋ�Â����Ƃ��K�v
�u����҉ۑ�v�̎�g�݂ɂ��ẮA��q�́u����҂̌����v�Ɋ�Â������g�݂ƂƂ��ɁA�Љ�I�ӔC�����Ɋ�Â������g�݂����߂��܂��B�ł��邾����̗�ʼn������߂���̂��l���Ă݂܂��傤�B
ex.�u���R�[���v�����{����ꍇ����҂̌����A�Љ�I�ӔC�����i�����ӔC�A����҂̗��Q�̑��d�Ȃǁj�ɂ�郊�R�[���ł��邱�Ƃ��K�v
�ːv���E�K�ȃ��R�[���A����������Ĕ��h�~��̎�g�݂Ɛ����A��g�݂̌��ʕA�\���ȋ~�ςȂǂ����߂��܂��B
![]()
- Q.CS�Ƃ��āA�u���q���܂̐��v�����Ƃɗ͂����Ă��邪�A����ŏ\���Ȃ̂��H
- A.����ɁA�u�����\�Ȕ��W�ւ̍v���v�̎��_�ŁA����҂Ƃ̃_�C�A���O�i�Θb�j�A�G���Q�[�W�����g�i�����j�A�R�~���j�P�[�V���������������i�߂čs�����Ƃ��d�v�ł��B
�� ����҂Ƃ̃_�C�A���O
���p��Ƃ��āA����҂ւ̉e����m��A����҂̉ۑ��m��A����҂̊��҂�m��A���邢�͎��g�D�i��Ɓj�̎�g�݂ɂ��ăR�~���j�P�[�V��������Ȃǂ�����܂��B
���Ƃ��A���S�Ȃǂɂ��ď���҂̒u����Ă��錻��𗝉����A�ϋɓI�ɏ��J�����Ȃ���A����̂��ǂ��W�Â���̂��߂̉ۑ����������Ȃǂ��l�����܂��B
�� ����҂Ƃ̃G���Q�[�W�����g
ISO26000�ł́u�Θb�̋@�����肾�����߂Ɏ��݂��銈���v�Ƃ��Ă��܂����A�i�g�D�i��Ɓj�ł͉ۑ���X�e�[�N�z���_�[�Ƌ������ĉ������Ă�����g�݂��s���Ă��܂��B�u�����\�ȏ���v��u����ҋ���v�Ȃǂ͊�Ƃ݂̂ł̎�g�݂͂ނ����������Ƃ���A�����������g�݂������\�Ȕ��W����w���i���邱�ƂɂȂ���ł��傤�B
�� ����҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V����
ISO26000�ł́A�Љ�I�ӔC�Ɋւ���R�~���j�P�[�V�������d�v�����Ă��܂��B���Ђ̂��q�l�݂̂Ȃ炸�L������҂ɑ��A�R�~���j�P�[�V�������邱�Ƃ�i�߂܂��B
CSR���݂̂Ȃ炸�AWeb�T�C�g�A���i���x���A����Ғc�̂Ƃ̈ӌ������ȂǑ��l�Ȏ�i�ɂ��H�v�����߂��܂��B
- ISO26000�ɂ��ƂÂ��u����҉ۑ�v�̎�g�݂̃��r���[
�E�u����҉ۑ�v�͂ł��Ă���̂�
�E�u����҉ۑ�v�̉���D�揇�ʂƂ��Ď��g�ނ�
�E���Ђ́u����҉ۑ�v�̎�g�ݗ� - �u����҉ۑ�v�𗝉����邽�߂̃��[�N�V���b�v�̊��E�^�c
�E�u����҉ۑ�v�͌o�c�S�̂Ɋւ��܂��B���q�l���傾���ł͂Ȃ��A�ł��邾�������̕��傩��Q���āA���[�N�V���b�v�Ȃǂɂ��f�B�X�J�b�V�����ŗ�����[�߂܂��傤�B
�E�e�[�}��
�@�@�� ���Ђ��ǂ̂悤�ȁu����҉ۑ�v�Ɏ�g�ނƂ�����
�@�@�� ��ƂƏ���҂̊W�̂�������l����